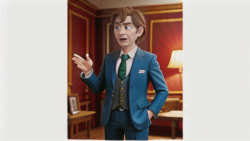法律
法律 補助参加:訴訟の裏側で動く第三者の影
裁判では、原告と被告という二つの当事者が争いますが、時には第三者が訴訟に関わる場合があります。これを補助参加と言います。補助参加とは、既に始まっている裁判に、その結果によって利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を支援する形で加わる制度です。例えば、AさんがBさんに土地の所有権を主張する裁判を起こしたとします。この時、CさんがBさんからその土地を借りているとしましょう。もしBさんが裁判に負けると、Cさんは土地を借り続けることができなくなるかもしれません。このような場合、CさんはBさんを支援するために補助参加人として裁判に加わり、Bさんが勝訴するように協力することができます。補助参加するためには、訴訟の結果によって、参加を希望する人の権利や義務に直接的な影響が生じる必要があるという点が重要です。単に当事者と仲が良い、あるいは仕事上の付き合いがあるといっただけでは、補助参加は認められません。あくまで、裁判の結果が、法律上、参加希望者の権利や義務に直接影響を与える場合のみ、補助参加が認められるのです。また、補助参加人は、あくまで当事者を支援する立場なので、主体的に訴訟を指揮することはできません。例えば、訴訟の取り下げや請求の変更などは、補助参加人ではなく、当事者自身が行う必要があります。あくまでも当事者の補助的な役割を果たす存在であり、当事者に代わって訴訟を主導することはできません。このように、補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、自らの権利を守るために裁判に関与できる制度です。当事者ではないものの、裁判の結果によって大きな影響を受ける可能性がある場合に、自分の権利を守るための重要な手段となるのです。