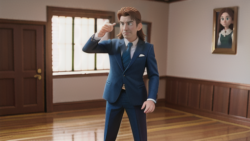離婚
離婚 離婚と債務名義:取り決めを守るための法的効力
お金の貸し借りや、誰かに何かを支払う義務があることを、きちんと証明する書類のことを債務名義と言います。債務名義は単なる借用書とは異なり、裁判所や公証役場といった公的な機関が作成したものなので、法律で認められた強い効力を持っています。このため、もし債務を負った人が支払いをしなかった場合でも、債権者はこの債務名義に基づいて、裁判所の手続きを通じて強制的に支払いを受けられます。具体的には、裁判所に申し立てを行い、債務者の銀行預金や給料、不動産などを差し押さえることで、債権を回収することが可能です。夫婦が離婚する場合、慰謝料や財産分与、子どもの養育費など、お金の支払いが発生することがよくあります。このような場合、口約束だけで済ませずに、債務名義を作成しておくことが非常に大切です。口約束だけでは、言った言わないの水掛け論になりやすく、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。また、債務者が支払いを拒否した場合、強制的に支払いを受けさせる手段が限られてしまいます。債務名義を作成することで、慰謝料や財産分与、養育費などの支払いについて、誰が誰に、いつ、いくら支払うのかといった権利関係をはっきりと示すことができます。これは、将来的な紛争を防ぐために非常に有効です。例えば、養育費の支払いが滞った場合、債務名義があれば、すぐに裁判所の手続きに進むことができ、スムーズに養育費の回収ができます。このように、債務名義は、離婚に伴う金銭的な取り決めを確実に履行するため、そして将来のトラブルを未然に防ぐための、重要な役割を果たすものと言えるでしょう。