遺族扶助料:公務員の遺族への支援

調査や法律を知りたい
遺族扶助料って、奥さんや子ども以外にも受け取れる人がいるんですか?

調査・法律研究家
はい、そうです。配偶者や子ども以外にも、順番が決まっていて、父母や、場合によっては祖父母なども受け取れる場合があります。

調査や法律を知りたい
順番はどうやって決まっているんですか?

調査・法律研究家
配偶者、未成年の子、父母、重度障害で所得の少ない成年の子、祖父母の順です。先に順位の高い人がいれば、その人が受け取ることになります。
遺族扶助料とは。
亡くなった公務員の方が退職後にもらえる年金(恩給)を受けていた場合、そのご家族は『遺族扶助料』を受け取ることができます。これは恩給法という法律で決められています。誰が受け取れるかは順番が決まっていて、まず配偶者(結婚している奥さんか旦那さん)、次に子ども(成人していない)、その次に両親、さらに体が不自由で収入が少ない成人した子ども、最後に祖父母となります。順番が前の人がいれば、後ろの人は受け取れません。
遺族扶助料とは

遺族扶助料とは、国や地方の役所の職員であった人が退職後に受け取っていた恩給の受給者が亡くなった場合、その遺族に支給されるお金のことです。これは、職員が長年国や地方のために働いてきたことへの感謝と、その遺族の暮らしを支えるための制度です。
恩給とは、簡単に言うと、職員が退職後、または仕事中に亡くなった場合に、その働きに報いるため、国や地方が支給する年金のようなものです。遺族扶助料は、この恩給と深く結びついており、恩給を受けていない場合は遺族扶助料も支給されません。つまり、亡くなった方が現役の職員であったり、退職後に恩給を受け取る資格がなかった場合には、遺族扶助料は支給されないということです。
この遺族扶助料の支給は、恩給法という法律に基づいています。この法律には、恩給を受け取れる条件や金額、支給の仕方などが細かく定められており、遺族扶助料についても詳しい規定があります。例えば、遺族扶助料を受け取れる遺族の範囲(配偶者、子どもなど)や、それぞれの遺族が受け取れる金額、支給が始まる時期や終わる時期などが、この法律で決められています。
遺族扶助料は、恩給を受け取っていた方が亡くなった後、その遺族の生活の安定を図るための大切な制度です。そのため、支給の条件や金額は法律によってきちんと定められています。もし、遺族扶助料についてもっと詳しく知りたい場合は、恩給法を確認するか、関係する役所(人事院など)に問い合わせてみると良いでしょう。担当者が丁寧に教えてくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺族扶助料とは | 国や地方の役所の職員であった人が退職後に受け取っていた恩給の受給者が亡くなった場合、その遺族に支給されるお金。職員の長年の勤務への感謝と遺族の生活支援を目的とする。 |
| 恩給とは | 職員が退職後、または仕事中に亡くなった場合に、その働きに報いるため、国や地方が支給する年金のようなもの。遺族扶助料の支給には恩給の受給が必須。 |
| 法的根拠 | 恩給法。受給条件、金額、支給方法など、遺族扶助料に関する詳細な規定が定められている。 |
| 恩給法の規定内容 | 遺族扶助料の受給資格のある遺族の範囲(配偶者、子どもなど)、各遺族の受給金額、支給開始時期と終了時期など。 |
| 遺族扶助料の目的 | 恩給受給者の死亡後の遺族の生活安定 |
| 問い合わせ先 | 人事院などの関係役所 |
受給資格者

遺族扶助料は、亡くなった恩給受給者の遺族が生活に困窮することを防ぎ、生活の安定を図るための制度です。この扶助料を受け取れる人を「受給資格者」と言い、法律によって厳密に定められています。
故人の親族であれば誰でも受給資格があるわけではなく、配偶者、子、父母、孫、祖父母など、法律で定められた特定の親族のみが対象となります。また、対象となる親族でも、いくつかの条件を満たす必要があります。
例えば、子は未成年の場合、または身体に重い障害があり、かつ収入が少ない成人の場合のみ受給資格を認められます。健康で自立した生活を送れる成人の子には、受給資格がありません。
受給資格者には順位が定められています。第一順位は配偶者、第二順位は子、第三順位は父母、第四順位は孫、第五順位は祖父母となります。もし第一順位の配偶者が生存している場合、第二順位以降の親族は受給資格がありません。配偶者がすでに亡くなっている場合や、そもそも配偶者がいない場合には、第二順位の子が受給資格を得ます。
このように、遺族扶助料は故人に最も近い親族から順番に受給資格が与えられます。これは、故人の扶養を受けていたと推定される範囲を考慮し、より生活の安定を必要とする者を優先的に保護するためです。
故人の兄弟姉妹は、たとえ故人と生計を同じくしていたとしても、受給資格はありません。法律で定められた範囲外の親族は、たとえ故人と深い関係にあったとしても、この制度の保護対象とはならないのです。
| 受給資格者 | 条件 | 順位 |
|---|---|---|
| 配偶者 | – | 1 |
| 子 | 未成年、または身体に重い障害があり、かつ収入が少ない成人 | 2 |
| 父母 | – | 3 |
| 孫 | – | 4 |
| 祖父母 | – | 5 |
| 兄弟姉妹 | 対象外 | – |
金額と手続き
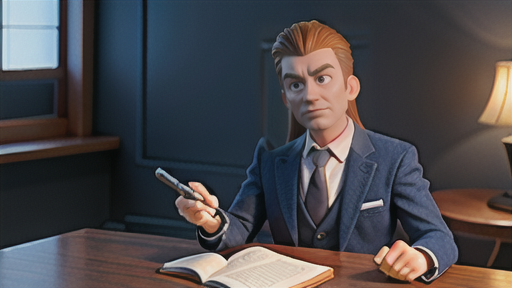
亡くなった家族を支えるための遺族扶助料は、亡くなった方が受け取っていた恩給の額によって金額が変わります。恩給額の一定の割合が遺族扶助料として支払われますが、その割合は家族構成や受給資格の順位によって法律で細かく定められています。例えば、配偶者の場合は恩給の半分が、子供の場合は4分の1が支給されるといった具合です。また、扶助を受ける家族が複数いる場合は、それぞれの受給割合に応じて分割して支給されます。
この遺族扶助料を受け取るには、決められた申請手続きが必要です。申請先は、亡くなった方が加入していた公務員の共済組合、または年金事務所です。申請に必要な書類としては、亡くなった方の死亡診断書や戸籍謄本、遺族扶助料を受け取る方の住民票などがあります。これらの書類を揃えて申請する必要があります。
さらに、遺族扶助料の請求には期限があります。亡くなった方の死亡を知った日から5年以内に申請しなければなりません。この5年という期限を過ぎてしまうと、たとえ受給資格があっても遺族扶助料を受け取ることができなくなります。ですので、申請を忘れてしまったり、期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。必要な書類を集め、申請期限内に手続きを済ませるようにしましょう。詳しい金額や手続きについては、それぞれの共済組合や年金事務所にお問い合わせいただくと、担当者が丁寧に案内してくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遺族扶助料の金額 | 亡くなった方が受け取っていた恩給の額によって変わる。恩給額の一定割合が支給され、割合は家族構成や受給資格の順位によって異なる。 例:配偶者→恩給の半分、子供→恩給の4分の1 |
| 申請先 | 亡くなった方が加入していた公務員の共済組合、または年金事務所 |
| 必要な書類 | 死亡診断書、戸籍謄本、住民票など |
| 申請期限 | 亡くなった方の死亡を知った日から5年以内 |
| 問い合わせ先 | 各共済組合または年金事務所 |
支給の停止

遺族扶助料は、家族を亡くした方が経済的に困窮することを防ぐための大切な制度です。しかし、状況が変わり、支えが必要でなくなったと判断された場合は、支給が止まります。
支給が止まる一番多い例は、受給資格のあるお子様が成人した場合です。成人すれば、自分で生計を立てられるようになると考えられるからです。また、重度の障害のあるお子様が、お医者様の診断で障害が回復したと認められた場合も、支給は止まります。これは、障害が回復すれば、就労などを通して経済的に自立できる可能性が高まると判断されるためです。
配偶者が再婚した場合も、支給は停止されます。再婚相手からの経済的な支援が見込めるようになるからです。しかし、再婚後に離婚した場合などは、一定の条件を満たせば再び支給を受けられることがあります。どのような場合に支給が再開されるのか、詳しいことは担当の窓口にお問い合わせください。
当然ですが、受給者の方が亡くなられた場合も、支給は停止されます。
遺族扶助料の支給停止は、制度の趣旨に照らし、限られた財源を本当に困っている方に届けるための大切な仕組みです。生活状況に変化があった場合は、速やかに担当の窓口にご連絡ください。状況に応じて必要な手続きやご相談を承ります。
| 事由 | 説明 |
|---|---|
| お子様が成人した場合 | 自分で生計を立てられるようになると考えられるため |
| 重度の障害のあるお子様の障害が回復した場合 | 就労などを通して経済的に自立できる可能性が高まると判断されるため |
| 配偶者が再婚した場合 | 再婚相手からの経済的な支援が見込めるようになるため。ただし、再婚後に離婚した場合などは、一定の条件を満たせば再び支給を受けられる場合あり |
| 受給者の方が亡くなられた場合 | – |
他の制度との関係

遺族扶助料は、国家公務員や地方公務員であった方が亡くなった場合、その遺族の生活を支えるための制度です。この制度は、国民皆年金や厚生年金といった広く知られる年金制度とは別の枠組みで運用されています。そのため、遺族扶助料を受け取っていたとしても、他の年金を受け取る資格があれば、両方を同時に受け取ることが可能です。
具体例を挙げると、亡くなった方が国民年金の加入者であった場合、その遺族は遺族基礎年金を受け取れます。また、亡くなった方が厚生年金の加入者であった場合、その遺族は遺族厚生年金を受け取れます。これらの年金は、遺族扶助料とは異なる法律に基づいて支給されるため、重複して受け取ることが認められています。
遺族扶助料は、公務員であった故人の遺族にとって特別な支援制度と言えるでしょう。他の年金制度と合わせて受給することで、より充実した保障を受けることができます。例えば、遺族基礎年金だけでは生活が厳しい場合でも、遺族扶助料が上乗せされることで、生活の安定につながります。また、遺族厚生年金と遺族扶助料の両方を受け取ることができれば、よりゆとりある生活を送ることも期待できます。
ただし、それぞれの年金制度には、受給資格や支給額に関する独自の規定があります。遺族扶助料の支給額は、亡くなった方の勤務していた期間や役職、遺族の人数などによって異なります。他の年金も、加入期間や収入などによって金額が変わります。そのため、ご自身の状況に合った制度の内容や受給できる金額を、担当窓口に確認することが重要です。窓口では、それぞれの制度の詳しい説明を受けられますので、疑問点を解消し、安心して手続きを進めることができます。
| 制度名 | 概要 | 受給資格 | 支給額 | 重複受給 |
|---|---|---|---|---|
| 遺族扶助料 | 国家公務員や地方公務員であった方が亡くなった場合、その遺族の生活を支えるための制度 | 公務員であった故人の遺族 | 亡くなった方の勤務していた期間や役職、遺族の人数などによって異なる | 他の年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)と重複して受給可能 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者であった方が亡くなった場合、その遺族に支給される年金 | 国民年金の加入者であった故人の遺族 | 加入期間や収入などによって異なる | 遺族扶助料と重複して受給可能 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の加入者であった方が亡くなった場合、その遺族に支給される年金 | 厚生年金の加入者であった故人の遺族 | 加入期間や収入などによって異なる | 遺族扶助料と重複して受給可能 |
