特別方式の遺言:いざという時の備え

調査や法律を知りたい
先生、『特別方式の遺言』って、どんなものですか?普通の遺言と何が違うんですか?

調査・法律研究家
良い質問だね。普段の遺言は、自分で書くか公証役場で作る必要があるけど、『特別方式の遺言』は、病気や事故などで死期が迫っているなど、特別な事情がある場合に、簡単に作成できる遺言のことだよ。

調査や法律を知りたい
つまり、具合が悪くて、自分で字が書けない時でも遺言を残せるってことですか?

調査・法律研究家
その通りだよ。例えば、死が近いと分かっている時に、3人以上の証人がいれば、そのうち1人に自分の遺言の内容を伝えて書いてもらうことができるんだ。それを他の証人も確認して署名と押印をすれば、正式な遺言として認められるんだよ。
特別方式の遺言とは。
簡単に言うと、『特別方式の遺言』というのは、特別な事情がある時に、簡単な方法で遺言を残せるように認められている遺言のことです。例えば、今にも亡くなりそうな場合、3人以上の証人がいれば、その中の1人に遺言の内容を伝えて、遺言として成立させることができます。遺言の内容を伝えられた人は、それを書き留め、もしくは見せて、他の証人全員が間違いがないかを確認し、承認した後に、証人全員が署名と押印をすることになっています。
特別方式の遺言とは

人生の終わりが近づいた時、自分の財産をどうするか、誰に託すか、といった意思をきちんと示すことはとても大切です。しかし、病気や事故など、思いがけない出来事で、通常の遺言書を作るのが難しい場合もあります。そのような時のために、法律では「特別方式の遺言」という制度が用意されています。これは、通常の方法よりも簡単な手続きで遺言を残せるようにしたものです。例えば、死が迫っている状況や、災害で孤立し、通常の方法では遺言を作れないといった差し迫った状況で使えます。
具体的には、「危急時遺言」「隔絶地遺言」「船舶遺言」「航空機遺言」「自書証書遺言」といった種類があります。危急時遺言は、病気などで急死の恐れがある場合に、証人3人以上の立会いのもと、口頭で遺言を伝え、証人に筆記してもらう方法です。隔絶地遺言は、離島や山間部など、公証役場へのアクセスが困難な場所で、証人2人以上の立会いのもと作成します。船舶遺言と航空機遺言は、それぞれ船舶や航空機の船長や機長に遺言を託す方法です。これらの遺言は一定の期間内に家庭裁判所で確認の手続きが必要です。一方、自書証書遺言は、いつでも自分で全文を書き、日付と氏名を記入し、押印することで作成できます。公証役場に行く必要がなく、最も手軽な方法と言えるでしょう。
特別方式の遺言は、通常の遺言よりも要件が緩やかになっている分、後日、紛争に発展する可能性も否定できません。例えば、危急時遺言の場合、証人の選定や筆記の内容によっては、真の意思を反映しているかどうかの判断が難しくなるケースもあります。また、隔絶地遺言も同様に、証人の信頼性や遺言内容の正確さが問われる可能性があります。そのため、可能であれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。しかし、やむを得ない事情で特別方式の遺言を選択する場合には、証人の選定や遺言内容の明確化など、十分な注意を払い、後々のトラブルを避けるよう心がけることが重要です。この制度があるおかげで、たとえ難しい状況でも、自分の意思を未来に残すことができます。遺言を残すことは、残された家族や大切な人のためだけでなく、自分自身の人格を守るためにも大切な行為と言えるでしょう。
| 遺言の種類 | 状況 | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 危急時遺言 | 急死の恐れがある場合 | 証人3人以上の立会いのもと、口頭で伝え、証人に筆記してもらう | 証人の選定や筆記内容によっては、真の意思を反映しているかどうかの判断が難しくなるケースも |
| 隔絶地遺言 | 離島や山間部など、公証役場へのアクセスが困難な場合 | 証人2人以上の立会いのもと作成 | 証人の信頼性や遺言内容の正確さが問われる可能性も |
| 船舶遺言 | 船舶内 | 船長に遺言を託す | 一定期間内に家庭裁判所で確認の手続きが必要 |
| 航空機遺言 | 航空機内 | 機長に遺言を託す | 一定期間内に家庭裁判所で確認の手続きが必要 |
| 自書証書遺言 | いつでも可能 | 全文を自筆し、日付と氏名を記入、押印 | 最も手軽な方法 |
口授による遺言

人生の最期を迎えるにあたり、自分の財産を誰にどのように託すのか。これは誰もが真剣に考えるべき大切な事です。財産を巡る争いを避けるためにも、遺言を残す事は非常に重要です。通常、遺言は文書で作成しますが、病気や怪我などで文字を書く事が難しい場合もあります。そのような場合に有効なのが、口頭で遺言の内容を伝える「口授」という方法です。
口授による遺言は、必ず三人以上の証人が必要です。これは、遺言者の真の意思を確実に反映し、後々のトラブルを防ぐための大切な決まりです。まず、遺言者は、これらの証人の前で、自分の財産を誰に、どのように残したいのかを、はっきりと伝えなければなりません。曖昧な表現は避け、具体的な内容を伝える事が重要です。この時、証人の一人が、遺言者の言葉を書き留めるか、速やかに記録に残す必要があります。録音機器の使用も考えられますが、法律で認められた方法かどうか、事前に確認が必要です。
記録した内容は、必ず遺言者本人と、他の証人全員に確認してもらわなければなりません。内容に間違いがない事を全員が確認した後、遺言者と証人全員が、文書に署名と押印をします。この手続きが全て完了した時点で、口授による遺言が正式に成立します。このように、複数人の証人が関わる事で、遺言内容の正確さと信頼性を高めているのです。口授という方法は、身体的な理由で文字を書く事が困難な場合でも、自分の意思を確実に伝える事ができる、大切な手段と言えるでしょう。

秘密証書による遺言
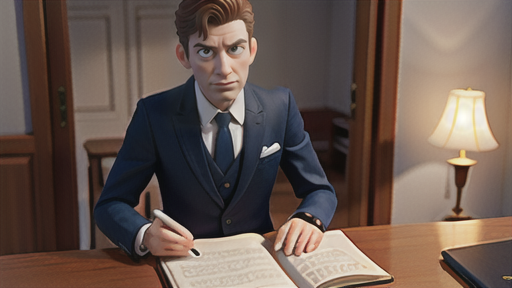
秘密を守る遺言の方法として、秘密証書による遺言があります。これは、遺言の内容を他者に知られたくない場合に有効な手段です。通常の遺言では、証人に内容を公開する必要がありますが、秘密証書遺言ではその必要がありません。
まず、遺言を作成する本人が、全文を自筆で書き、署名と押印を行います。パソコンやワープロで作成した文書は無効となりますので、注意が必要です。次に、証人2人以上の前で、この文書が自分の遺言書であることを明確に伝えます。ただし、この段階では証人に内容を伝える必要はありません。「これは私の遺言書です」と述べるだけで十分です。その後、遺言書を封筒に入れて封印します。
封印した封筒には、遺言者と証人全員が署名と押印をします。これは、封筒が開封されていないことを証明するために行います。万が一、封筒に開封の痕跡があった場合、その遺言は無効となる可能性があります。証人は、遺言の内容を知らなくても構いませんが、遺言者が自分の意思で作成し、封をしたことを証明する重要な役割を担います。
このように、秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしながら、確実に遺志を伝えることができる方法です。遺言の内容を家族や親族に知られたくない場合や、複雑な家庭環境にある場合などに適しています。ただし、全文の自筆、署名、押印、証人2人以上の存在、封筒への署名押印など、必要な手順がいくつかありますので、手続きに不備がないよう、事前に専門家へ相談することをお勧めします。

緊急時の遺言

不慮の事故や思いもよらない事態に見舞われた際に、残された家族のために自分の意思を伝えたいと願うことは、当然の心情と言えるでしょう。そのような切羽詰まった状況下で、財産の分配や後見人などを定めるために有効な手段として、「緊急時の遺言」という制度が用意されています。
この緊急時の遺言は、例えば船や飛行機の事故、あるいは感染症の広がりといった、一刻を争う差し迫った状況下で利用できます。通常の遺言に比べて、非常に簡略化された手続きで作成できる点が大きな特徴です。
まず、証人となる人が一人必要です。この証人の前で、自分の遺言の内容を口頭で伝えます。証人は、伝えられた内容を正確に筆記しなければなりません。そして、筆記した内容が間違いなく伝えられた内容と一致していることを確認し、証人自身が氏名と捺印をします。こうして緊急時の遺言が完成します。
通常、遺言を作成するには、証人が三人以上、もしくは二人以上必要となります。しかし、緊急時の遺言の場合には、状況の差し迫っている点を考慮して、証人が一人でも有効となります。これは、法で定められた特別な措置です。
人生には予期せぬ出来事がつきものです。そのような緊急事態に直面した場合でも、速やかに自分の意思を表明し、大切な家族に想いを伝えられるよう、法律によってしっかりと守られた制度と言えるでしょう。
ただし、この緊急時の遺言は、状況が落ち着いてから三か月以内に、家庭裁判所へ申し立てて、検認してもらう必要があります。これを怠ると、せっかく作成した遺言も無効になってしまうので注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 不慮の事故や思いもよらない事態に見舞われた際に、残された家族のために自分の意思を伝えるための制度 |
| 利用できる状況 | 船や飛行機の事故、感染症の広がりなど、一刻を争う差し迫った状況 |
| 特徴 | 通常の遺言に比べて手続きが簡略化されている |
| 作成手順 | 証人1人の前で遺言内容を口頭で伝え、証人が筆記し、氏名と捺印をする |
| 証人の人数 | 通常は3人以上または2人以上必要だが、緊急時は1人で有効 |
| 有効期限 | 状況が落ち着いてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てて検認が必要 |
特別方式の注意点

特別方式の遺言は、例えば遭難や病気など、緊急事態において柔軟に対応できるという大きな利点があります。しかし、その手軽さゆえに、いくつか注意しておかなければならない点が存在します。
まず、証人の選定には細心の注意が必要です。例えば、口授による遺言の場合、推定相続人や受遺者、それらの配偶者や直系血族は証人となることができません。これは、遺言の内容を自分に有利になるように仕向ける可能性があるためです。また、秘密証書遺言の場合にも、証人には同様の制限があり、さらに未成年者も証人になることができません。このように、証人の資格には様々な制限があるため、遺言作成時には誰に証人を依頼するか慎重に検討する必要があります。
さらに、特別方式の遺言は、それぞれ必要となる証人の人数や手続きが異なります。例えば、危急時遺言では証人が3人必要ですが、死期が迫っている場合の遺言では2人で認められます。また、口授による遺言は、証人が筆記することができない場合には、公証人が作成することになっています。このように、それぞれの方式によって必要となる手続きが異なるため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
そして、最も重要な点は、特別方式の遺言は、通常の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)に比べて、無効と判断されるリスクが高いということです。証人の資格や手続きに不備があった場合、せっかく作成した遺言が無効になり、故人の意思が尊重されないという事態になりかねません。ですから、可能であれば、通常方式で遺言を作成しておくことが最善です。
しかし、どうしてもやむを得ない事情で特別方式の遺言を選択しなければならない場合は、手続きを正確に行うことが何よりも大切です。不明な点があれば、法律の専門家である弁護士や司法書士、または公証人に相談し、助言を受けることを強くお勧めします。適切な知識と準備をもって遺言を作成することで、あなたの大切な想いを確実に未来へと繋ぐことができるのです。
| 種類 | メリット | デメリット・注意点 | 証人 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 特別方式の遺言 (危急時遺言、死期が迫っている場合の遺言、口授による遺言、秘密証書遺言など) |
緊急事態において柔軟に対応できる |
|
|
|
