弁済費用:どちらが負担する?

調査や法律を知りたい
『弁済の費用』は、誰が負担するのですか?

調査・法律研究家
原則として、お金を返す義務のある債務者が負担します。例えば、お金を返す時にかかる手数料などがこれにあたります。

調査や法律を知りたい
いつも債務者が負担するのですか?例外はありますか?

調査・法律研究家
はい、例外があります。例えば、お金を返してもらう人が引っ越しをして、お金を返すための費用が増えてしまった場合、増えた分の費用は引っ越しをした人が負担します。つまり、債権者が費用増加の原因を作った場合は、その増加分を負担するのです。
弁済の費用とは。
お金を返すのにかかる費用について、法律では、特に約束していなければ、返す人が負担すると決めています。ただし、お金を受け取る人が引っ越しなどをして、返すためのお金が増えてしまったときは、増えた分は受け取る人が負担することになっています。
弁済費用の原則
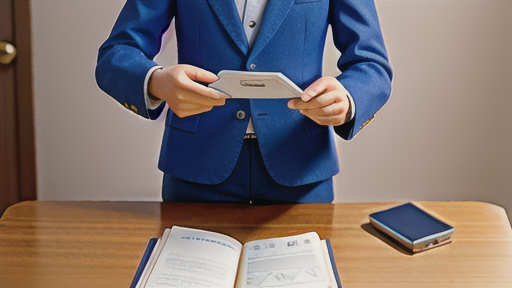
お金の貸し借りや物の売買など、私たちの暮らしの中で交わされる様々な約束事を法律では「契約」と呼びます。そして、契約によって発生した義務を果たすことを「弁済」といいます。例えば、お金を借りたのであれば返す、物を買ったのであれば代金を支払う、といった行為が弁済にあたります。この弁済には、時としてお金がかかる場合があります。例えば、遠方に住む人に送金する場合の送金手数料や、買った物を郵送してもらう場合の送料などが挙げられます。では、これらの弁済にかかる費用は一体誰が負担するべきなのでしょうか。法律では、特に何も取り決めがない限り、原則としてこれらの費用は債務を負っている側、つまり「債務者」が負担することになっています。
具体的に考えてみましょう。お金を借りた場合、借りたお金を返す、つまり債務を履行するために必要な費用は、借りた人が負担しなければなりません。例えば、銀行振込で返済する場合、振込手数料は借りた人持ちとなります。また、インターネットで買い物をした場合、購入した商品を届けてもらう、つまり売買契約における債務を履行するために必要な送料は、買った人持ちとなります。このように、債務者は、債務を完全に履行する責任を負っているため、弁済にかかる費用も負担する必要があるのです。
ただし、当事者間で事前に異なる取り決めをしていた場合は、その取り決めに従うことになります。例えば、売買契約において、送料は売り手が負担することで合意していた場合は、売り手が送料を負担することになります。また、債権者側の都合で弁済場所が変更になった場合など、債務者の責めに帰すべからざる事由によって弁済費用が増加した場合には、債権者がその増加分を負担することになります。このように、弁済費用は原則として債務者が負担しますが、状況によっては例外も存在します。契約内容をよく確認し、疑問点があれば専門家に相談することが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約 | お金の貸し借りや物の売買など、暮らしの中で交わされる様々な約束事。 |
| 弁済 | 契約によって発生した義務を果たすこと (例: 借りたお金を返す、商品の代金を支払う)。 |
| 弁済費用 | 弁済に際して発生する費用 (例: 送金手数料、送料)。 |
| 弁済費用の負担 |
|
費用の増加と負担

お金のやり取りには、しばしば様々な費用が発生します。例えば、品物を送る場合には送料がかかり、お金を振り込む際にも手数料が発生することがあります。これらの費用は、一体誰が負担するべきなのでしょうか?多くの場合、借りたお金を返す人は、返すためのかかる費用も負担することになります。これを「弁済費用」と言います。
しかし、返す側が常に全ての費用を負担するとは限りません。法律では、貸している側の都合で費用が増えた場合は、増えた分は貸している側が負担するべきだと定められています。
例えば、貸している側が最初に指定していた受け取り場所を変更し、その変更のために送料が増えたとします。この場合、増えた送料は貸している側が負担しなければなりません。
また、別の例として、貸している側が海外に引っ越し、送金手数料が通常よりも高くなったとしましょう。この場合も、増えた手数料は貸している側が負担することになります。返す側は、本来負担すべき費用に加えて、増えた費用まで負担する必要はありません。
ここで重要なのは、費用の増加が本当に貸している側の都合によるものかどうかという点です。返す側の都合、あるいはどちらの都合でもない理由で費用が増えた場合は、増えた費用も返す側が負担することになります。
例えば、返す側が指定した期日にお金を用意できず、延滞料金が発生した場合、これは返す側の責任となります。また、予期せぬ災害や経済の変動によって送料や手数料が値上がりした場合、これはどちらの都合でもないため、原則として返す側が負担することになります。
このように、弁済費用は、誰が費用増加の原因を作ったのかによって、誰が負担するかが決まります。費用負担について疑問が生じた場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。適切な知識を持つことで、不必要な費用負担を避けることができるでしょう。
| 費用の種類 | 負担者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 弁済費用 (返すためのかかる費用) | 返す人 | 通常の送料、手数料 |
| 貸す人 | 貸す人の都合で変更になった受取場所への送料の増加分、貸す人の都合で発生した高い送金手数料 | |
| 延滞料金 | 返す人 | 返す人が期日にお金を用意できなかった場合 |
| 予期せぬ費用増加 | 返す人 | 災害や経済変動による送料・手数料の値上がり |
当事者間の合意の重要性

お金のやり取りに関わる揉め事を避けるためには、契約を結ぶ時点で費用負担についてしっかり話し合い、はっきりさせておくことが大切です。具体的に誰が、どんな費用を、いくら負担するのかをきちんと決めておくことで、後々トラブルになるのを防ぐことができます。
特に、高額な費用が発生する可能性のある取引や、貸す側と借りる側の間に特別な事情がある場合は、契約書に費用負担について明記しておくことが望ましいです。例えば、不動産の売買や、事業のための融資など、大きなお金が動く場合は、契約書の作成を強くお勧めします。また、当事者の一方に経済的な困難があったり、特別な事情がある場合も、契約書を作成することで、将来のトラブルを避けることができます。
口約束だけでは、言った言わないの水掛け論になりやすく、後で問題になる可能性があります。言った言わないという状況になった場合、どちらの主張が正しいのかを証明することは非常に困難です。契約書を作成することで、双方が合意した内容を証拠として残すことができますので、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書は、将来発生するかもしれない紛争を予防するだけでなく、円滑な取引を実現するための重要なツールです。契約書を作成することで、当事者間の信頼関係を築き、よりスムーズな取引を行うことができます。また、費用負担について疑問点や不明な点がある場合は、法律の専門家に相談することも有効な手段です。専門家は、法律の知識に基づいて適切なアドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぐためのサポートをしてくれます。弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することで、より確実な形で契約を進めることができます。
| お金のトラブルを防ぐためのポイント | 詳細 |
|---|---|
| 費用負担の明確化 | 契約時に、誰が、どんな費用を、いくら負担するのか? 特に高額な費用が発生する可能性がある、または特別な事情がある場合は、契約書に明記する。 |
| 契約書の重要性 | 口約束は言った言わないになりやすい。 契約書は合意内容の証拠となり、トラブルを未然に防ぐ。 |
| 契約書のメリット | 将来の紛争予防 円滑な取引の実現 信頼関係の構築 |
| 専門家への相談 | 疑問点や不明な点は法律の専門家(弁護士、司法書士など)に相談。 |
事例で考える費用の負担

売買契約における費用の負担について、具体的な例を用いて考えてみましょう。例えば、山田さんが田中さんに物を売る契約を結んだとします。この時、送料については特に何も決めていなかったとしましょう。商品の運搬にかかる費用は、原則として買い手の田中さんが負担することになります。これは、民法の売買に関する規定に基づく考え方です。
しかし、様々な状況によって、費用の負担者が変わる可能性があります。例えば、田中さんが引っ越しをしたために、当初予定していた届け先よりも遠くの場所へ商品を送ることになったとします。この場合、引っ越しによって送料が増額した分については、田中さんの都合によるものなので、田中さんが負担することになります。田中さんが引っ越しをしていなければ、送料の増額は発生しなかったからです。
一方、山田さんが商品を誤って別の場所に送ってしまった場合を考えてみましょう。このせいで、商品を正しい届け先に送り直すための費用が余分にかかったとします。この場合の追加送料は、山田さんのミスによるものなので、山田さんが負担することになります。もし山田さんが商品を正しい場所に送っていれば、追加の送料は発生しなかったからです。
このように、費用の負担を決める上で重要なのは、費用の増加が誰の都合によるものなのかをしっかりと見極めることです。契約時に送料について明確に決めていなかったとしても、事後の状況の変化や当事者の行為によって、費用の負担者が変わる可能性があることを理解しておく必要があります。
| 状況 | 費用の増加要因 | 費用の負担者 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 商品の運搬費用 | 買い手(田中さん) | 民法の売買に関する規定 |
| 買い手の引っ越し | 引っ越しによる送料増額分 | 買い手(田中さん) | 田中さんの都合による送料増加 |
| 売り手の誤配送 | 再送費用 | 売り手(山田さん) | 山田さんのミスによる送料増加 |
まとめ

お金を返す際には、基本的には借りた人が返すためのお金も負担します。例えば、お金を返すためにかかる手数料や交通費などです。しかし、貸した人の都合で費用が増えてしまった場合は、増えた分は貸した人が負担しなければなりません。
例えば、遠くまでお金を返しに来てもらうように指定したり、特定の送金方法を指定することで手数料が高くなってしまったりした場合です。このような場合、本来必要なかった費用を借りた人に負担させるのは公平ではありません。
お金の貸し借りをする際に、誰がどの費用を負担するのかを、あらかじめきちんと決めておくことが大切です。口約束だけでなく、契約書に書いて残しておくと、後々「言った」「言わない」のトラブルを防ぐことができます。契約書には、費用の種類や金額、誰が負担するのかを具体的に明記しましょう。
お金の返し方や費用負担について、法律で細かく決まっている部分もあります。複雑な契約や高額な取引の場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。自分自身で判断するのが難しい場合は、早めに相談することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
お金の貸し借りにおける費用負担のルールは、円滑な取引を行うためにとても重要な役割を果たしています。借りた人も貸した人も、それぞれの立場や状況を理解し、適切な費用負担を行うように心がけましょう。また、疑問点があれば、すぐに専門家に相談することで、より安心して取引を行うことができます。曖昧なままにせず、きちんと確認することで、信頼関係を築き、スムーズな取引を実現できるでしょう。
| お金の返済時の費用負担 | 解説 | 注意点 |
|---|---|---|
| 原則 | 借りた人が返済にかかる費用(手数料、交通費など)を負担 | 貸し手の都合で費用が増加した場合は、貸し手が負担 |
| 費用の増加例 |
|
本来不要な費用を借り手に負担させるのは不公平 |
| 契約時の費用負担 | 事前に誰がどの費用を負担するかを明確に決定 | 口約束だけでなく、契約書に明記(費用の種類、金額、負担者) |
| 法律と専門家 | 費用負担の一部は法律で規定、複雑な契約や高額取引の場合は専門家への相談推奨 | 専門家は法律に基づいたアドバイスを提供 |
| 円滑な取引 | お互いの立場や状況を理解、適切な費用負担 | 疑問点は専門家に相談 |
