文書提出命令:真実を明らかにする力

調査や法律を知りたい
先生、『文書提出命令』って、当事者以外にも出せるんですか?

調査・法律研究家
はい、出せますよ。文書を持っている人が裁判の当事者じゃなくても、裁判に必要な証拠となる文書を持っている場合は、裁判所から『文書提出命令』が出されることがあります。

調査や法律を知りたい
へえ、そうなんですね。でも、勝手に人のものを見ちゃっていいんですか?

調査・法律研究家
いいえ、勝手にではありません。裁判所は、文書を持っている人に質問をして、本当に必要な証拠かどうかを確認した上で、命令を出します。ですから、関係ない文書まで無理やり提出させられるわけではありませんよ。
文書提出命令とは。
裁判で証拠となる書類について、裁判所が書類を持っている人に提出を求めることを「書類提出命令」といいます。書類を持っている人が裁判の当事者でない場合は、裁判所はその人に尋ねた上で命令を出さなければいけないと決まっています。
文書提出命令とは

民事裁判では、何が真実かを明らかにし、正しい判決を出すために、様々な証拠を用います。中でも書かれたものは、誰にも変わらない事実を示す強い証拠となることが多く、裁判の結果に大きな影響を与えます。しかし、必要な書類が相手方の手にあり、お願いしても提出してもらえない場合はどうすれば良いのでしょうか。このような時、「文書提出命令」という制度があります。これは、裁判所が証拠となる書類を持っている人に対し、裁判所に提出するように命じるものです。
相手方が簡単には証拠を出さない場合でも、裁判所の命令があれば、事実を明らかにすることができます。例えば、ある人が交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせたとします。この時、事故を起こした人が加入している保険会社は、事故の状況を記録した書類を持っているかもしれません。相手方は、事故を起こした人に損害賠償を求める裁判を起こした際に、裁判所を通じて保険会社にこの書類の提出を命じるよう求めることができます。このように、この命令は、裁判を起こしている当事者だけでなく、関係のない第三者に対しても出すことができます。
例えば、お金を貸したのに返してもらえないという事件で、お金を借りた人が、ある会社に勤めているとします。そして、給与の支払状況が争点になった場合、裁判所は会社に対して給与明細の提出を求めることができます。また、事件に関係する銀行が取引記録を持っている場合、裁判所は銀行に対しても提出命令を出すことができます。
文書提出命令は、裁判をスムーズに進め、正しい判決を下すために重要な役割を果たしています。これにより、一方的に不利な状況に置かれることなく、証拠に基づいた公正な裁判を受けることができます。
| 文書提出命令 | 説明 | 対象 | 例 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 裁判所が証拠となる書類を持っている人に対し、裁判所に提出するように命じる制度 | 裁判の当事者、関係のない第三者 | 交通事故の際、保険会社が持つ事故状況の記録/給与支払状況が争点の場合の会社の給与明細/事件に関係する銀行の取引記録 |
| 目的 | 裁判をスムーズに進め、正しい判決を下すため/一方的に不利な状況に置かれることなく、証拠に基づいた公正な裁判を受けるため | 証拠の提出が困難な場合 | 相手方が証拠となる書類を提出しない場合など |
命令の対象となる文書

裁判における証拠開示手続きの一つである文書提出命令は、訴訟に関連するあらゆる種類の文書を対象としています。命令の対象となる文書の種類は幅広く、特定の種類に限定されないことを理解しておくことが重要です。具体的には、契約書、領収書、請求書といった公式な書類はもちろんのこと、電子メール、手紙、メモ書きなども含まれます。近年の情報技術の発展に伴い、電子メールや交流サイトの書き込み、写真、動画といった電子データが重要な証拠となる事例が増加しています。そのため、これらの電子データも文書提出命令の対象となります。紙媒体の文書だけでなく、電子データも証拠となり得ることを認識しておく必要があります。
例えば、売買契約に関する訴訟であれば、売買契約書本体だけでなく、契約締結に至るまでの交渉過程が記録された電子メールや、当事者間の口約束をメモした手帳なども対象となります。また、貸金返還請求訴訟では、借用書だけでなく、返済状況が分かる銀行の取引明細書や、当事者間の金銭のやり取りを記録した手帳、領収書なども対象となるでしょう。さらに、名誉毀損訴訟では、問題となった発言が掲載された出版物やウェブサイトの画面、交流サイトへの書き込みなども証拠として重要になります。このように、訴訟の種類や内容に応じて、様々な文書が証拠となり得るため、関連する可能性のある文書は幅広く検討する必要があります。
また、文書提出命令の対象は、文書そのものだけでなく、文書の存在を証明したり、文書の内容を裏付ける資料も含まれます。例えば、文書の原本が存在しない場合、その文書が存在していたことを証明する証言や、文書のコピー、内容を覚えている人の記憶なども対象となり得ます。また、文書の内容が真実であることを示すために、関係者の証言録取書や、写真、動画なども提出を求められる場合があります。このように、直接的な証拠だけでなく、間接的な証拠も含めて、訴訟の真相解明に役立つ可能性のある資料は、文書提出命令の対象となる可能性があります。命令に従って適切な文書を提出することは、裁判の公正な判断のために不可欠です。
| 文書提出命令の対象 | 種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 文書そのもの | 紙媒体 | 契約書、領収書、請求書、手紙、メモ書き、手帳 |
| 電子データ | 電子メール、交流サイトの書き込み、写真、動画 | |
| ウェブサイトの画面、出版物 | ||
| 文書の存在を証明する資料 | 存在証明 | 証言、文書のコピー、記憶 |
| 内容裏付け | 証言録取書、写真、動画 |
第三者への命令

裁判における文書提出命令は、争っている当事者だけでなく、関係のない第三者に対しても出すことができます。これは、訴訟の真相解明のために必要な情報を幅広く集めることを目的としています。例えば、ある事件について重要な情報を持っている会社や団体、個人が書類を持っている場合、裁判所はそれらの第三者に対して、持っている書類の提出を命じることができます。
しかし、第三者に対してこのような命令を出す場合には、裁判所は必ず事前に第三者から事情を聴かなければなりません。これは、関係のない第三者の権利や利益を守るために非常に大切な手続きです。例えば、書類の内容によっては、業務上の秘密や個人のプライバシーに関わる情報が含まれている可能性があります。そのため、裁判所は第三者の言い分を丁寧に聞き、提出を求める書類の内容や、その書類が訴訟とどれくらい関係があるのかなどをしっかりと見極めた上で、命令を出すかどうかを判断します。
第三者も命令に従うことで訴訟に巻き込まれる可能性があるため、慎重な手続きが求められます。例えば、裁判所は、提出を求める書類の範囲を必要最小限に絞ったり、秘密保持のために特別な措置を講じたりするなど、第三者の負担をできる限り軽減する努力を払う必要があります。また、第三者には、命令に納得できない場合に異議を申し立てる権利も保障されています。このように、第三者に対する文書提出命令は、訴訟の公平性と第三者の権利保護のバランスを保ちながら、慎重に進められる必要があります。もし、第三者から求められた場合は、まずは弁護士等の専門家に相談する事をお勧めします。
命令に従わない場合

裁判所から書類の提出を求められたにもかかわらず、きちんとした理由もなく従わないと、厳しい結果を招くことがあります。これは、裁判のルールを破ったとみなされ、罰を受ける可能性があるということです。
どのような罰があるかというと、まず、提出しない側の言い分を裁判所が認めなくなるということがあります。これは、提出を求められた書類が、裁判で自分の主張を裏付ける重要な証拠だった場合、その主張が認められず、裁判に負けてしまう可能性が高くなることを意味します。
次に、金銭的な罰が科されることもあります。これは、裁判所への提出を怠ったことへの罰金のようなもので、場合によっては高額になることもあります。
さらに、状況によっては、刑事罰、つまり犯罪として扱われ、罰せられる可能性もゼロではありません。これは、特に悪質な場合や、裁判の妨害とみなされる場合に考えられます。
裁判所の命令に従わないことは、自分にとって不利なだけでなく、裁判全体のスムーズな進行を妨げることにもなります。裁判は、決められたルールに従って行われる必要があり、一方がルールを守らないと、公平な判断ができなくなってしまいます。
また、裁判所の命令に従わないという事実は、その人の信頼性を大きく損なうことにもなります。裁判に限らず、社会生活を送る上で、約束を守ること、決められたルールに従うことは非常に重要です。裁判所の命令に従わないという行為は、その人が信頼できない人物であるという印象を与え、将来様々な場面で不利に働く可能性があります。
そのため、裁判所から書類の提出を求められた場合は、すぐに対応し、もし何らかの事情で提出が難しい場合は、速やかに裁判所に連絡を取り、事情を説明することが大切です。そうすることで、不要なペナルティを避け、スムーズに裁判を進めることができます。
| 裁判所命令への不対応 | 結果 |
|---|---|
| 書類不提出 |
|
| 提出困難な場合 | 裁判所へ速やかに連絡し事情説明 |
関連する法律
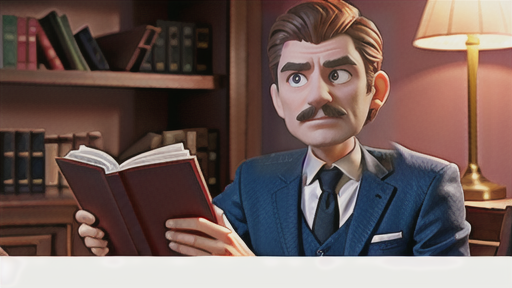
裁判で真実を明らかにするために、必要な書類や証拠品を裁判所に提出させる手続きがあります。これを文書提出命令といいます。この手続きは、民事訴訟法という法律に基づいて行われます。民事訴訟法とは、個人が争っている問題を裁判で解決するためのルールを定めた法律です。この法律があることで、裁判が公平に行われるようになっています。
文書提出命令に関する詳しいルールは、民事訴訟法の198条から201条に書かれています。どこにどのようなことが書かれているのでしょうか。まず、どんな種類の書類が提出命令の対象になるのかが具体的に書かれています。次に、裁判所が命令を出すための手順、そして命令に従わなかった場合、どのような罰則があるのかなども細かく定められています。
裁判では、証拠調べがとても大切です。何が真実なのかを明らかにするために、様々な証拠を調べます。この証拠調べをスムーズに進めるために、文書提出命令は欠かせない制度です。例えば、ある会社が別の会社を訴えたとします。訴えられた会社が持っている契約書が、裁判で重要な証拠になる場合、裁判所は訴えられた会社に対して、その契約書を提出するように命令を出すことができます。もし、会社が命令に従わず契約書を提出しない場合、裁判所は罰金を科したり、訴えられた会社の主張を認めなかったりといった対応をとることができます。このように、文書提出命令は真実を明らかにするための重要な役割を担っているのです。関連する法律をよく理解し、正しく使うことが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き名 | 文書提出命令 |
| 根拠法 | 民事訴訟法 |
| 民事訴訟法とは | 個人の争いを裁判で解決するためのルール |
| 関連条文 | 198条〜201条 |
| 条文の内容 | 提出対象書類の種類、裁判所の命令手順、命令違反の罰則 |
| 証拠調べとの関係 | スムーズな証拠調べに欠かせない制度 |
| 例 | 訴えられた会社が持つ契約書が重要証拠の場合、裁判所は提出命令を出す |
| 命令違反への対応 | 罰金、主張の却下など |
| 役割 | 真実を明らかにするための重要な役割 |
