債権譲渡:知っておくべき落とし穴

調査や法律を知りたい
『債権譲渡の対抗要件』って、難しくてよくわからないです。誰が誰に何をすればいいんですか?

調査・法律研究家
そうですね、少し複雑ですね。簡単に言うと、AさんがBさんにお金を貸していて(AさんはBさんからの債権を持っている)、その債権をCさんに譲ったとします。このとき、CさんがBさんにお金を返してもらうには、AさんがBさんに譲渡したことを伝えなければなりません。これが通知です。または、Bさんが譲渡を承諾する方法もあります。

調査や法律を知りたい
なるほど。AさんがBさんに伝える、またはBさんが認める必要があるんですね。でも、第三者への対抗要件の『確定日付のある書証』というのはどういうことですか?

調査・法律研究家
例えば、CさんがBさんへの債権をDさんに譲ったとします。この場合、DさんがBさんに対して債権を主張するには、CさんがDさんに譲渡したことを証明できる、日付が明確な書類が必要になります。これが確定日付のある書証です。確定日付のある書証がないと、DさんはBさんに対して債権を主張できない可能性があります。
債権譲渡の対抗要件とは。
お金を払う義務がある人に、その権利が誰かに移ったことを伝えるには、権利を移した人からお金を払う義務がある人へ、その事実を知らせるか、お金を払う義務がある人にその移ったことを認めてもらう必要があります。また、お金を払う義務がある人以外の人にも主張するためには、日付のはっきりとした証拠となる書類で知らせたり、同意を得たりする必要があります。
譲渡の効力発生の条件
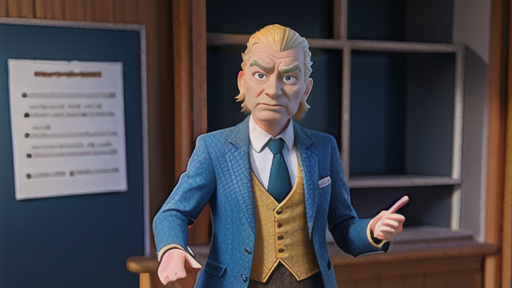
金銭の受け渡しを約束する権利、いわゆる債権を他の人に渡すことを債権譲渡と言います。これは、今現在持っている債権だけでなく、将来発生する売掛金なども対象となります。しかし、譲渡の合意をしたからといって、すぐにその効力が発生するわけではありません。いくつかの条件を満たす必要があります。
基本的には、譲渡する人と譲り受ける人の間で合意が成立すれば、譲渡の効力は発生します。これは、当事者間で交わした契約に基づくものであり、お金を支払う義務のある人の同意は必要ありません。誰に支払うかはお金を支払う人の問題ではなく、お金を受け取る権利を持つ人同士の問題であるという考え方によるものです。
しかし、譲渡によってお金を支払う人の負担が増えるような場合には、その人の同意が必要になります。例えば、お金を支払う期日や方法が変わる場合です。支払う人の同意なしに、一方的に支払条件を変更することは許されません。これは、支払う人の負担を一方的に増やすことを防ぐためです。例えば、元々年末にまとめて支払うことになっていたものを、毎月分割で支払うように変更されると、支払う人は毎月支払う手間が増えます。また、手数料の負担なども発生する可能性があります。このような債務の内容の変更を伴う譲渡は、債務者の保護のために同意が必要となるのです。
債務者への対抗要件

お金を貸した人が、その権利を別の人に譲ることを債権譲渡といいます。譲渡する人と譲り受ける人の間では、両者の合意だけで債権は有効に譲渡されます。しかし、お金を借りた人に対しては、譲渡を主張するためにはさらに条件が必要です。これは、借りた人が二重に支払いをさせられることを防ぐためのものです。
具体的には、譲り受けた人は、借りた人に債権が譲渡されたことを知らせるか、借りた人から譲渡の承諾を得る必要があります。知らせを受けた、あるいは承諾した時点で、借りた人は誰にお金を返せば良いのかがはっきりと分かります。もし、借りた人が譲渡されたことを知らずに、元のお金を貸した人に返済してしまった場合、譲り受けた人は借りた人にもう一度支払いを求めることはできません。なぜなら、借りた人には何の落ち度もないからです。
債権譲渡の通知は、内容証明郵便など、確実に相手に届いたことが証明できる方法で行うことが望ましいでしょう。口頭での通知は、後々トラブルになる可能性があります。また、承諾を得る場合も、書面で残しておく方が安全です。譲渡の通知や承諾は、借りた人を保護する上で非常に重要です。譲り受けた人は、確実に通知または承諾の手続きを行い、後々のトラブルを避けるようにしなければなりません。知らないうちに別の人に債権が渡っていて、二重に支払いを要求されるのは、借りた人にとって大きな負担となるからです。そのため、法律では、借りた人を保護するためにこのような仕組みが設けられています。
第三者への対抗要件

お金を貸した相手が、そのお金を受け取る権利を他の人に譲ってしまうことがあります。これを債権譲渡と言います。しかし、この譲渡は、お金を貸した本人だけでなく、周りの人にも影響を与える可能性があります。そのため、周りの人、つまり債務者以外の人に対してはこの譲渡を主張するためには、より厳しい条件が必要になります。
譲渡を周りの人に主張するためには、譲渡があったことを伝える通知か、その譲渡を認める承諾が必要です。そして、その通知か承諾には、いつ書かれたものかハッキリと分かる証拠が必要です。この証拠のことを「確定日付のある書証」と言います。確定日付のある書証とは、文書が作られた日を確実に証明できる書類のことです。例えば、公証役場で作成される公正証書や、郵便局で送る内容証明郵便などがこれにあたります。
では、なぜこのような確定日付のある書証が必要なのでしょうか。それは、第三者に対する債権譲渡を公に示す方法としての役割を果たすからです。確定日付があることで、譲渡がいつ行われたのかが明確になります。もし、同じ債権について複数の譲渡があった場合、この確定日付によってどの譲渡が先に行われたのかを判断できるのです。
例えば、AさんがBさんに100万円貸したとします。BさんはCさんとDさんに、Aさんからの100万円の受け取り権利を譲ると約束しました。Cさんは3月1日、Dさんは3月5日に、それぞれBさんから譲渡の通知を受けたとします。もし、Dさんだけが確定日付のある書証を持っていた場合、AさんはDさんに100万円を支払う義務が生じます。このように、確定日付のある書証は、債権をめぐる争いを防ぎ、取引の安全を守るためにとても重要なのです。確定日付のある書証がないと、誰に債権があるのか分からなくなり、混乱が生じる可能性があります。そのため、債権譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付のある書証が不可欠です。
確定日付の重要性

お金を貸した権利を他の人に譲るとき、譲ったという事実をきちんと証明できることがとても大切です。これを証明する書類には、いつそれが作られたのかがはっきり分かるようにしておく必要があります。これが「確定日付」と呼ばれるものです。
例えば、AさんがBさんに貸したお金の権利をCさんに譲ったとします。このとき、確定日付のある書類で譲渡の事実を証明できれば、CさんはBさんにお金を請求できます。しかし、もし確定日付のない書類で手続きした場合、後からDさんが同じ権利をBさんから譲り受けたと主張した場合、どちらの譲渡が先に行われたのかを証明するのが難しくなります。
もしDさんが確定日付のある書類を持っていたら、Cさんは自分の権利を主張できず、Bさんにお金を請求できなくなる可能性があります。
特に、Bさんがお金を返せなくなるような事態、例えば自己破産などをした場合、この確定日付の有無が非常に重要になります。確定日付があるかないかで、お金を取り戻せるかどうかが決まってしまうからです。
債権を譲り受ける人は、将来のトラブルを避けるため、必ず確定日付のある書類で手続きを行うべきです。確定日付を得る方法はいくつかあります。公証役場で確定日付印をもらう方法、内容証明郵便で送る方法などです。自分に合った方法を選び、確実に日付が証明できる方法を選ぶことが大切です。確定日付は、お金を貸した権利を確実に守るための、とても大切な手続きなのです。
| 債権譲渡における確定日付の重要性 |
|---|
| お金を貸した権利(債権)を他の人に譲渡する際、譲渡の事実と日時を証明することは非常に重要です。 |
| 譲渡を証明する書類には、作成日時が明確に分かる「確定日付」が必要です。 |
| 確定日付がない場合、複数の譲受人が現れた際に、誰が先に権利を取得したかを証明することが困難になります。 |
| 特に、債務者が自己破産などした場合、確定日付の有無が債権回収の可否を左右します。 |
債権譲受人は、トラブル防止のため、確定日付のある書類で手続きを行うべきです。
|
| 自分に合った方法を選び、確実に日付が証明できる方法を選ぶことが大切です。 |
実務上の注意点

金銭の受け渡しに関する権利を譲り渡す際には、幾つかの大切な点に気を配る必要があります。まず譲渡を禁じる約束事が定められている権利は、そもそも譲り渡すことができません。契約書などで譲渡が禁じられている場合は、その権利は譲り渡す対象から外れます。そのため、事前に契約内容をよく調べておくことが重要です。
次に、権利を譲り渡したことを、お金を支払う義務のある人に確実に伝える必要があります。もし、相手が譲渡の事実を知らなければ、二重に支払いが行われてしまう危険があります。そのため、配達の記録が残る、内容証明郵便のような方法で伝えるのが安全です。
また、権利の譲渡に関する契約書を作る際には、譲り渡す権利の内容、金額、日付などをはっきりと書く必要があります。あいまいな書き方をすると、後々争いごとの原因になる可能性があります。そのため、明確で詳しい内容を記載するように心がけるべきです。
さらに、譲渡に関係する税金についても考える必要があります。譲渡によって得た利益にかかる税金や、物の売買にかかる税金が発生する可能性があります。そのため、事前に税金の専門家に相談しておくことをお勧めします。これらの点に注意することで、権利の譲渡を円滑かつ安全に行うことができます。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 譲渡禁止の確認 | 契約書などで譲渡が禁止されている権利は譲渡できないため、事前に契約内容を確認する。 |
| 債務者への通知 | 権利を譲り渡したことを債務者に確実に伝える(例:内容証明郵便)。二重支払いを防ぐため。 |
| 契約書の作成 | 譲渡する権利の内容、金額、日付などを明確に記載する。あいまいな記載は後の争いごとに繋がる。 |
| 税金 | 譲渡によって発生する税金(譲渡所得税、消費税など)について、事前に税金の専門家に相談する。 |
